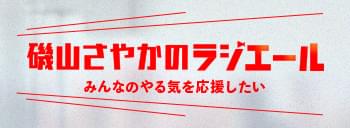企業理念を構成する価値観の一つとして“やる気のある人を広く受け入れ、結果に報いる組織を作ります”の一分を掲げ、多様な人材を雇用してきたオープンハウスグループ。これと近しい価値観のもと、障がい者やシングルマザーを含め、幅広い人材を雇用し注目を集めているのがチョコレートブランド・QUONチョコレートです。
同ブランドの雇用姿勢にシンパシーを覚えたオープンハウスグループは、グループ企業であるプロバスケチーム・群馬クレインサンダーズのバレンタインキャンペーンへの協力を打診。ご快諾をいただき、コラボレーションが実現しました。
今回は、このキャンペーンの振り返りも兼ねて、QUONチョコレートを運営する一般社団法人ラバルカグループ代表理事の夏目浩次さんと広報の山本幸代さんにお話を伺いました。
-

夏目 浩次
QUONチョコレート代表
2003年、愛知県豊橋市において障害者雇用の促進と低工賃からの脱却を目的とするパン工房(花園パン工房ラ・バルカ)を開業。
2014年久遠チョコレート事業を立ち上げ、わずか5年で全国33拠点に拡大。「全ての人々がかっこよく輝ける社会」を目標に、様々な企業へ経営参画し企業連携・事業開発に取り組みながら障害者の雇用、就労促進を図っている。2003年、愛知県豊橋市において障害者雇用の促進と低工賃からの脱却を目的とするパン工房(花園パン工房ラ・バルカ)を開業。
2014年久遠チョコレート事業を立ち上げ、わずか5年で全国33拠点に拡大。「全ての人々がかっこよく輝ける社会」を目標に、様々な企業へ経営参画し企業連携・事業開発に取り組みながら障害者の雇用、就労促進を図っている。 -

山本 幸代
広報
久遠チョコレートの広報担当者。
本プロジェクトの窓口として、社内外の調整や各種やり取りをご担当。久遠チョコレートの広報担当者。
本プロジェクトの窓口として、社内外の調整や各種やり取りをご担当。
シンプルに、お客さまを楽しませるチョコレート屋。人権や平等を声高に叫ぶつもりはない。
― QUONチョコレートをまだ知らない方のために、どういった活動をされているのか教えてください。
いろんな紹介の仕方をしていただくのですが、自分自身ではチョコレート屋です、とお答えしています。
チョコレートを自社で企画・製造するメーカーであり、自社のショップや併設のカフェで提供する小売業・飲食業でもあります。ショップは直営・フランチャイズを合わせて全国に41店舗(2025年3月現在)が営業しているほか、百貨店のチョコレートフェアに出展することもあります。
― 障がい者、シングルマザー、難病児の親御さんなど、働きづらいご事情をお持ちの方々を積極的に雇用されていることでも知られています。
はい、いろいろな背景のスタッフが働いています。ただ、それを前面に出したくはないんです。僕らとしては、社会貢献だとか、ナントカ支援だとは思っていなくて。人権だ平等だと力んで言うつもりもありません。働きたい人、頑張りたい人に、そうする選択肢がある社会のほうがシンプルだし、かっこいいでしょって思うから、まず自分で実践しているだけなんです。
だからお客さまにも、難しいこと抜きに、ただのチョコレート屋として楽しんでいただきたいんです。商品やサービスが気に入ったから買う、食べる。僕らの背景を知っていても知らなくても、満足できる。そんなブランドでありたいと思っています。
― お客さまを楽しませるために、商品やサービスをつくる際に心がけていることはありますか?
選ぶ楽しみを提供することです。看板商品のQUONテリーヌはフレーバーは常時30種類、季節や地域を限定して販売したフレーバーも含めると累計170種類以上をつくってきました。テリーヌ含め、全部の商品を1枚1個から購入していただけます。
また、単に種類が多いだけでなく、繊細な差を楽しんでいただけるようなものづくりも特徴です。主原料であるカカオ1つとっても、ワインのブドウやコーヒー豆のように、産地や年、発酵のさせ方で全然違う味や香りを持っているんです。その違いを楽しんでいただくために、いろんな産地のカカオを仕入れ、ピュアな配合でつくったシリーズを展開しています。
少量多種で販売しているため、お客さまは今日は何を買おう、どれとどれを組み合わせようと迷われます。そういった楽しい悩みの時間を過ごしていただけることが、QUONの価値だと考えています。

多様性が、少量多種のものづくりの原動力。
― 少量多種のものづくりができるのはなぜでしょうか?
製造工程のほとんどを自社内で行っていて、かつ手作業の比率が大きいからです。チョコレートの製造工程のなかでも特に時間がかかるのが、一定の温度帯に保ったチョコレートを丹念に混ぜることで、結晶のサイズを整えるテンパリングです。単純な作業ではあるのですが、時間と労力が大きいため、多くの会社は機械化しています。ですが、その機械はすごく大きく、ある産地のカカオを小量だけ扱うということができません。QUONでは、この作業を障がい者をメインとした社内スタッフが人力で行っています。複雑な作業は苦手でも、粘り強さはピカイチという人材たちが活躍してくれているおかげで、少量からカカオを扱うことができ、様々な産地のカカオを使ったバリエーション豊かな商品づくりが可能になっているというわけです。
また、副原料としてフルーツや茶葉を混ぜ込む際には、それらを粉砕し粉状にする必要がありますが、これも専用の機械を持っている業者さんにお願いするのが一般的です。この場合も、少量では引き受けてもらえません。特定の産地や特徴的な育て方のイチゴが手に入ったとしても、他のイチゴと混ぜないと粉末化できないのです。結果、「国産イチゴ使用」等のおおまかな区分での表記の商品が出来上がります。一方、私たちはLABOと呼ぶ自社工場で、石臼を使って副原料を粉に挽いています。ごく少量から粉にできますし、機械に比べ摩擦熱が小さいため食材の味が落ちることもありません。

― 多様な人材を採用していることが、事業にもプラスに働いているのですね。
はい、そう思います。ただ、狙って設計したというよりも、結果的にそうなってくれたという感覚が近いかもしれないですね。
LABOにしても、多様性を事業に活かそうと思ってはじめたわけではなくて、あるスタッフが当時の事業所内で働き続けてもらうのが難しくなったときに、なにか力を発揮できる場所をつくれないかと藻掻くなかで立ち上がったというのが実際のところです。後に、チョコレートブランドとしてのQUONの独自領域が必要だよねとなったときに、LABOがうまく噛み合ってくれたんです。時間をかけて模索してきたことが積み重なって、ブランドの個性になっていると感じます。
「社会貢献ブランド」から脱皮するために一番を目指す。
― チョコレート屋として目標はありますか?
一番になろうと言っています。より具体的に、日本最大級のチョコレートの祭典「アムール・デュ・ショコラ」で一番になるという言葉もよく口にしますね。コンテストではないので順位が付けられるわけではないですし、基準も売上や客数などの数値化できるものから、どれだけのお客さんがそのブランド目当てで来場するかなど、いろいろ考えられます。それでも当事者である出展者同士では、なんとなくの序列を共有しているように感じます。僕らは今、だいたい真ん中ぐらいかなと思っています。
― なぜ一番を目指すのですか?
社会の意識を変えるきっかけになりたいからです。できない人なんていなくて、社会のほうが工夫をしていけば、誰だって活躍できるんだということを、キレイゴトとしてではなく、事実として証明したいんです。そのために、一番というインパクトが必要です。
QUONは今、世の中から社会貢献ブランドという風に見られていると思っています。メディアでご紹介いただく際の切り口はほぼ雇用がテーマですし、同業者からもどこか別枠として捉えられているというか、ライバルとして見られていません。
そう認識されたままだと、どんなに会社を大きくしようと、有名になろうと、社会の意識は変わらないと思うんです。社会貢献的な側面で下駄を履かされてるんだろうと言えてしまうから。だから、商品とサービスでの評価で一番になって、社会貢献ブランドではなく、チョコレートブランドとして認識されたいんです。
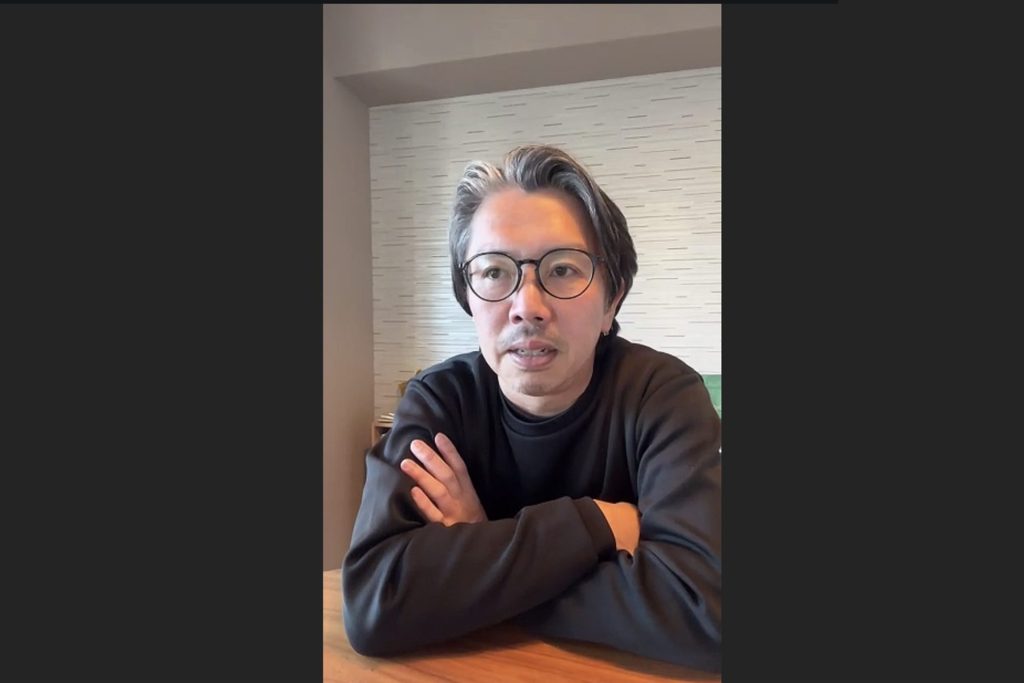
応援という言葉はあまり使わないけれど、奥底にある想いには共感を覚える。
― O-EN HOUSE PROJECT の一環として行った、群馬クレインサンダーズのバレンタインキャンペーンについて質問させてください。オープンハウスグループからの最初の連絡にご対応くださったのが、広報の山本様だと伺いました。最初に相談内容をご覧になったとき、率直にどんな感想を抱かれましたか?
山本様:大きなお話をいただいたな、と。正直なところ、お声がけいただいたタイミングには、バレンタイン用のご発注はすでに締め切っていました。チョコレート業界にとっては一番の繁忙期ですから、通常期よりも長めに納期をいただくものでして。私たちは製造工程に手作業が多いので、製造速度に浮き沈みがあることもあって、間に合わせられるかなという心配が勝りましたね。
ただ、O-EN HOUSE PROJECTはどんな取り組みなのか、なぜ私たちにお声がけいただいたのかについて丁寧な説明をいただいたこともあって、お引き受けしたいなという気持ちもあり、代表に相談することにしました。といっても、夏目は「やる」一択だろうなと確信しつつの相談でしたが(笑)
― 実際、夏目様は「やる」とおっしゃったのでしょうか?
はい。僕も僕で、現場のみんなは「夏目はやる一択だろう」と分かったうえですでに実現方法を考え始めているんだろうな、なんて思っていました。
山本様:そのとおりです(笑) ですから夏目には相談だけして特に議論などはせず、すぐに製造現場との話し合いをはじめました。みんなも前向きで、間に合わせる方法が見つかったので、受託する旨をご回答しました。
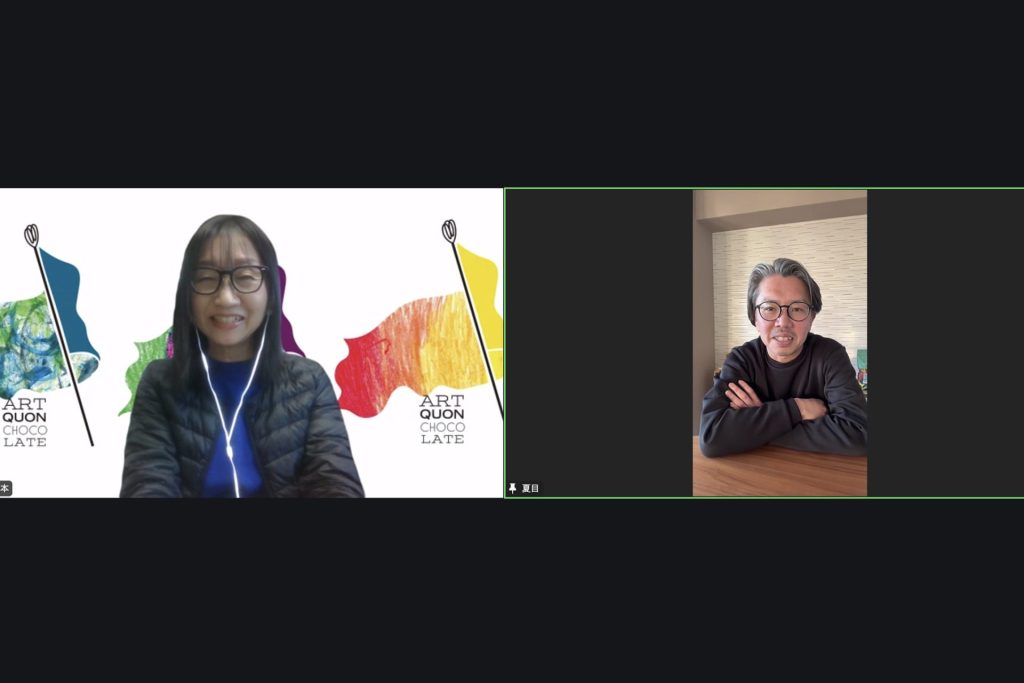
― 前向きに考えていただけたのはなぜですか?
取り組みの主旨に共感するところがあったのと、それを説明する文面から熱い想いを感じました。ご発注量からも本気さが伝わったことも大きいですね。
もちろん自分たちの製造のリズムだったり都合だったりはあるので、どうしても無理なことはあります。ただ、大きなチャンスをいただいたら、どうやったらできるんだろうと考えてみるのがQUONの文化です。そうやってチーム全体が考え、工夫していくことで、成長してきたと思っていますから。
― 主旨に共感いただいたという点について、詳しく聞かせてください。
あくまで僕が知っている範囲でですが、オープンハウスさんには何か似た匂いを感じていまして。応援とか、挑戦とか、そういった言葉を大事にされている点ですね。
僕たち自身は、誰かを応援するという言葉はあまり使いません。応援する側、される側という関係ではなく、それぞれを活かし合うために一緒にがんばるという感覚だからです。すべてのスタッフに挑戦を求めることもしません。挑戦らしい挑戦をしていないように見える人も、毎日を必死にがんばっているのを知っているからです。
ただ、使う言葉が違うだけで、奥底にある想いには共通するところがすごく多いように感じるんです。勝手に思っているだけですけれど。

一流とは、関わることが誇らしく思えること。
― 私たちとしても、QUONチョコレートさんにシンパシーを感じる部分が多くあります。
一例として、夏目さんの著書『温めれば、何度だってやり直せる』のなかに「一流ブランド」を目指すという言葉が登場しますが、オープンハウスグループも2024年に「なろうぜ、一流」というスローガンを掲げていました。「一流」は数字で定義できない抽象度の高い概念ですが、夏目さんにとって「一流」とはなんでしょうか?
関わる方が誇りに思えることかなと思います。関わる方というのは、お客さまであり、スタッフやその家族であり、お取引先であり、いろいろな立場の方のことです。お客さまが、QUONのチョコレートを誰かにプレゼントするときに、誇らしいと感じられること。スタッフが、このブランドで働いていることを、誇らしいと思えること。材料や包材を収めてくださる業者さんが、このブランドに選ばれることを誇らしいと思えること。商品を仕入れてくださるお店が、このブランドを扱えることを誇らしいと思えること。
いろんな側面がありますが、関係を築くことが誇らしいと思ってもらえる存在は、一流だと思います。
― 今後、どうやって一流ブランド、つまり誇らしいブランドに近づいていきますか?
難しいんですが、やっぱり人と人であることを大事にすることなのかなと思っています。目先の利益や効率を重視して、人を置き去りにするようなブランドは、資本は大きくなっても、一流には近づけないのではと思います。
人間関係が続いていくと、良いことも悪いことも、喜びも悲しみも、成功も失敗もいろいろ起こります。関係がまずくなったときにこそ、正面から向き合っていくことが、一流に近づく道なんじゃないかなと感じますね。

誰かの「かなえたい」を応援したい。
がんばる皆さんの想いに寄り添うサポート活動、
それがO-EN HOUSE PROJECTです。
What We Do