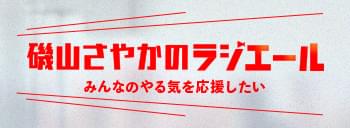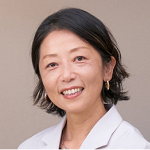東京都国立市を拠点に、30年以上にわたり活動する「社会福祉法人かいゆう」。「しょうがいのある人が、地域で自分らしく生きる」を掲げ、障がいを持つ人たちを幅広くサポートしています。
その取り組みに共感したオープンハウスグループは、冠協賛した「東京ヤクルトスワローズ 応燕プロジェクト(2025年8月開催)」でノベルティグッズとして配布したリストバンドの制作の一部を「かいゆう」に依頼しました。
そんなご縁のある「かいゆう」の理事長である池田希咲さんに、福祉の道を歩むことになったきっかけや現在の取り組み、そして持続可能な社会福祉経営への挑戦についてお話を伺いました。
(2025年9月に取材)
目次 / CONTENTS
-

池田 希咲
社会福祉法人かいゆう理事長
埼玉県出身。2005年より「特定非営利活動法人くじら雲」で約10年間、管理者兼支援員として勤務。2017年には「特定非営利活動法人FLAGS FLAGS design」の設立に参画。20年以上にわたり障がい福祉の現場に携わり、2020年からはフリーランスのソーシャルワーカーとしても活動。同年、「社会福祉法人かいゆう」企画室に加わり、2023年に理事就任。2024年6月より現職。社会福祉法人かいゆう理事長
埼玉県出身。2005年より「特定非営利活動法人くじら雲」で約10年間、管理者兼支援員として勤務。2017年には「特定非営利活動法人FLAGS FLAGS design」の設立に参画。20年以上にわたり障がい福祉の現場に携わり、2020年からはフリーランスのソーシャルワーカーとしても活動。同年、「社会福祉法人かいゆう」企画室に加わり、2023年に理事就任。2024年6月より現職。
「福祉のプロフェッショナルになる!」と決めた
― 「社会福祉法人かいゆう」は30年以上の歴史があると伺っています。どんな取り組みをしているのかお聞かせください。
私たちは東京都国立市を拠点として、障がいを持つ方々がその軽重にかかわらず、暮らしたい地域で生涯にわたって生き生きと暮らすための支援をしています。1992年に前身となるボランティア団体からスタートし、NPO法人を経て、2011年に「社会福祉法人かいゆう(以下、かいゆう)」を設立しました。
現在は、障がいを抱えた20〜50代の生活を支援するグループホームや、小学1年生から高校3年生までを対象にした放課後等デイサービス、相談支援、通所型の生活介護など、計13の障がい福祉事業を運営しています。
かつては障がいのある人が暮らす場といえば施設や病院が中心でしたが、今は自宅やグループホームなど地域型へと移行しつつあります。それでも「親亡きあと、この子はどう暮らしていくのか」という不安は、多くの家庭が抱える課題です。また、65歳になると介護保険の受給対象となりますが、これに切り替えることでこれまで利用していた障がい福祉サービスの一部が使えなくなってしまい、その結果、生活が困難になってしまうケースも少なくありません。「かいゆう」はこうした課題に向き合い、子どもから大人になり、そして親亡きあとまでも、地域で安心して暮らし続けられるよう、切れ目なく支援を届けることを目指しています。

―池田さんが福祉の道を歩み始めたきっかけを教えてください。
私の場合、両親ともに福祉職に就いていたことが大きく影響しています。母は障がい者入所施設の看護師、父は、職業訓練を通して障がいや病気を抱える人たちを支える施設の施設長を務めていました。
1990年代当時は、今のような制度が整っていなかったので、休みの日には一緒に出かけたり食事をするなど、両親に連れられ様々な障がい者、介助者の方と過ごす時間は日常でした。
仕事として、支援者としてだけではなく、地域で共に暮らす者として関わる両親の姿を見て育ったので、自分も福祉の道に進むのはごく自然な流れだったというか。
―なるほど。確固たる意思を持ってこの道を選ばれたのかと思いきや、どちらかというと自然な成り行きだったんですね。
そうですね。ただ、あるタイミングで「やるからには福祉のプロフェッショナルになりたい!」とスイッチが入ったんです。それは26歳のとき、「かいゆう」の前身である「特定非営利活動法人くじら雲(以下、くじら雲)」で日中デイサービスの立ち上げに携わり、管理者兼支援員として働き始めた頃のことです。行政とさまざまな折衝を行う中で、「若いから」「女性だから」と舐められているように感じてしまって。それが嫌だったので、相手が真剣に向き合わざるを得ないくらいにプロとしての力をつけるしかない、と腹をくくりました。まぁ、ただの負けず嫌いです(笑)。
やってみたら、そこから世界が大きく広がりました。育児と仕事を両立しながら通信大学で学び、介護福祉士、社会福祉士に続けて、精神保健福祉士や公認心理師の資格も取得しました。「かいゆう」で約10年経験を積んだのち、いったん外に出て他の事業所の立ち上げに携わり、さらに、フリーランスとして精神科のソーシャルワーカーや障がい者雇用のアドバイザー、成年後見、生活困窮者支援も手がけるなど、幅広い活動に携わることができました。
崖っぷちから持続可能な福祉へ挑戦
―その後、「かいゆう」に復職し、2024年には理事長に就任されました。
就任を決めたのは、資金面で非常に厳しい状況にあった「かいゆう」を立て直すためです。多くの社会福祉法人が厳しい経営に直面し、閉鎖や合併、譲渡が相次ぐ中、「かいゆう」も例外ではありませんでした。かといって、簡単になくすわけにはいきません。
「かいゆう」内外での活動を通じて、本当にさまざまな障がいや生きづらさ、困難な課題を抱える方々と出会い、そのたびに、支援がどれほど必要とされているかを痛感しました。もし、私たちが倒れて支援が滞ったら、困るのは利用者です。
「かいゆう」は社会福祉法人として、公的資金を基盤に地域福祉を支える責任があります。いざとなれば譲渡や合併という選択肢もありますが、まずは自分たちの力で立て直したい。崖っぷちの厳しい状況も、持続可能な福祉経営に挑戦するチャンスと考え、理事長就任を決意しました。

―持続可能な福祉経営のために、今、取り組まれていることは何でしょうか?
まずは、より多くの暮らしのニーズに応えていけるための体制づくりです。地域には支援を待っている方がまだまだたくさんいらっしゃいますが、人材が不足している現状では、支援依頼をお断りせざるを得ないケースも発生しています。
「断らないかいゆう」「支援の持続」を実現するには、新規の支援をどんどん開拓し、「この人は、ここはできる」「ここはサポートが必要」と利用者の特性を見極め素早く支援のフレームをつくり、次の支援員に引き継ぐ。そしてすぐに次の支援を開拓する。こうしたサイクルを回せるチームづくりが不可欠です。支援員には、目の前の利用者だけでなく、地域で支援を待つ多くの人たちにも目を向けながら動くことが求められます。
その一歩として今、支援員のみなさんに、社会福祉法人の運営を支える「制度」を学んでもらうことから始めています。大事なのは、支援員一人ひとりが障がい福祉サービス報酬や、補助金が地域の税金、社会保障によって支えられていることを理解し、自分たちの支援は地域から託された大切な役割なのだと自覚すること。そうした意識を持てたら、どうすれば一人でも多くの利用者を受け入れられるか、自ら考えて動けるようになります。
かくいう私も、最初からその意識を持てたわけではありません。20代で「くじら雲」の管理者兼支援員をしていた頃、赤字事業の収益化を求められながらも、そのためにサービスを削ったり事業転換したりすることに納得できず……。目の前の利用者のことだけを考えて突き進んだ結果、行き詰まり、離れることを選びました。
その後、別の事業所で補助金申請や支援員の給与計算、予算管理といった制度運営や経営実務を一通り経験する機会を得て、ようやく気づいたのです。支援がすべてではない。制度や経営という基盤があってこそ、支援が持続できるのだと。
外に出たからこそ気づけたことですが、今、医療・介護の現場はもう本当に深刻な人手不足です。私のように辞めなければ気づけない状況は、絶対に避けたい。支援員が中にいながら学び、やりがいを感じ、キャリアアップしていける環境の整備が、今の私に課せられた最重要のミッションです。

応援は連鎖するもの。応援されたら応援したくなる
― 今後、挑戦していきたいことはありますか?
障がいのある方の暮らしや「かいゆう」の取組について、自分の言葉で語れる支援員を増やすことです。地域の人たちに「○○さんはこんな人生を歩んでいる」「こんなことができる」「私はこういう支援をしている」という風に、障がい者一人ひとりの人生や個性、自分たちの支援のスタンスを語ることによって、地域は障がい者を特別な存在ではなく「ともに生きる地域の仲間」として受けとめられるようになると考えています。
そのための一番の近道は、「かいゆう」を知らない地域の人から「かいゆうって何をしているんですか?」と聞かれて、支援員が答える機会を重ねることです。だから今、支援員をどんどん地域に送りこんで、同業者だったり、街の商店だったり、いろんな方々と交流する場を設けているんです。慣れないことに戸惑う支援員もいますが、自分の仕事を見つめ直し、その意義を再認識する良いきっかけにもなっていると感じています。
障がい者が地域で生き生きと暮らせることは、「かいゆう」の課題であると同時に、地域全体の課題でもあります。地域を巻き込み、お互いを尊敬し合い助け合いながら、誰もが自分らしく暮らせる社会をともにつくっていけたら。そう考えています。
―障がい者の地域生活、そして事業の立て直し。大きな課題に立ち向かうその原動力は何でしょうか?
私を育ててくれた「かいゆう」や地域への恩返しをしたい、そして「障がいのある人の可能性を伝えたい」という気持ちです。障がい者は決して弱い存在ではありません。「こうしたい」という意思や夢を持ち、誰かの役に立ちたいと願っています。ただ、一人で実現するのは難しくて、「迷惑をかけるから」と諦めたり、「自分にはできない」と思いこんでいたり。でも、本当はやればできるんです。
だから私は「出かけたいなら、家族にちゃんと伝えてヘルパーを手配すればいいんだよ」「反対されても、諦めることはないよ」と伝えてきました。「大丈夫、できるよ」とエールを送り、一人ひとりの自己実現を全力で応援したい。その気持ちが原動力になっています。
―オープンハウスグループの「挑戦する人や組織を応援する」という企業姿勢に通じるものを感じます。
本当にそう思います! 応援は連鎖するものだと思います。自分はこんなに応援されているんだと感じたら、今度は自分も誰かを応援したくなりますよね。そんな風にバトンがつながれていくのは、素敵なことだなって。私はこれからも、障がい者や支援員の挑戦をしっかりと応援していきたい。隣に寄り添い、失敗も含めて一緒にチャレンジを楽しんでいけたらと思っています。
―そんな池田さんから、すでにチャレンジしている人、そしてまだ踏み出せずにいる人へ、メッセージをお願いします。
チャレンジするのに、成功や完璧にこだわらなくてもいいと思うんです。ゴールに向かって全力疾走しなくても、ゆっくり歩いて進んだっていい。一歩踏み出した先に広がる、新しい景色を楽しんでもらえたら。そのチャレンジを、きっと誰かが見ていて応援してくれるはずです。


誰かの「かなえたい」を応援したい。
がんばる皆さんの想いに寄り添うサポート活動、
それがO-EN HOUSE PROJECTです。
What We Do